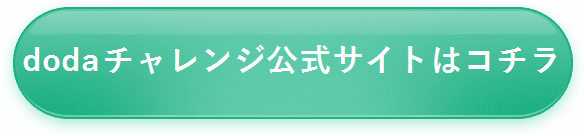dodaチャレンジで断られた!?断られる人の特徴や断られた理由について解説します

dodaチャレンジを利用しようと思ったのに、まさかの「ご紹介できる求人がありません」というお断りメールを受け取った経験はありませんか?転職活動において、希望を持って登録したサービスから断られると、正直へこみますよね。
でも、安心してください。
これはあなただけの話ではなく、意外と多くの方が経験していることなんです。
断られてしまう理由にはいくつかのパターンがあり、それを知ることで、次の一歩を踏み出すヒントが見えてくるはずです。
今回は、dodaチャレンジで断られてしまう人の特徴や、その背景にある理由を詳しく解説していきます。
断られる理由1・紹介できる求人が見つからない
転職エージェントの中でもdodaチャレンジは、障害者雇用に特化した求人を扱っています。
そのため、一般の転職サイトと比べて取り扱う求人数や企業の条件がある程度限られているのが現状です。
「求人が見つからない」と断られてしまう場合、希望条件と企業側のニーズがマッチしていないケースが多いんですね。
これはdodaチャレンジのサービスに問題があるわけではなく、マッチングの難しさからくるものであり、今のご自身の条件と市場のニーズのギャップを見つめ直す機会とも言えます。
希望条件が厳しすぎる(在宅勤務限定、フルフレックス、年収500万円以上など)
近年、在宅勤務やフルフレックスといった働き方が注目されるようになりましたが、これらを絶対条件にしてしまうと、紹介できる求人がかなり限られてしまいます。
特にdodaチャレンジでは、障害者雇用枠の求人が中心のため、まだまだ柔軟な働き方を提供している企業は多くありません。
加えて、年収500万円以上といった高年収条件も求人数を大きく絞ってしまう要因になります。
理想の働き方を叶えたいという気持ちはよく分かりますが、まずは条件の優先順位を見直してみることで、新たな選択肢が見えてくることもあるんです。
希望職種や業種が限られすぎている(クリエイティブ系、アート系など専門職など)
「どうしてもこの仕事がしたい!」という強いこだわりを持っている方もいらっしゃいますよね。
特にクリエイティブ職やアート系などの専門職は、元々求人数が少ない上に、障害者雇用として募集されることが少ない分野でもあります。
そのため、求人が見つからず、紹介が難しいという結果になることもあるんです。
専門性を活かした仕事を探すこと自体は素晴らしいことですが、少しだけ視野を広げて「他にも自分にできることはないか?」と柔軟に考えてみることも大切です。
新たな可能性に気づけるかもしれませんよ。
勤務地が限定的(地方で求人自体が少ない)
希望勤務地が地方や人口の少ないエリアに限定されている場合、どうしても企業の母数が少ないため、紹介できる求人も限られてきます。
特に障害者雇用に積極的な企業は、都市部に集中している傾向があります。
地方での転職を希望する場合、地元密着型のハローワークや、自治体の支援機関を併用することも視野に入れてみると良いかもしれません。
dodaチャレンジだけにこだわらず、複数の窓口を持っておくことで、思わぬ出会いがあることもあるんです。
断られる理由2・サポート対象外と判断される場合
dodaチャレンジは、障害者雇用に特化した転職支援サービスのため、サポート対象となる条件がある程度定められています。
そのため、場合によっては「サポートの対象外と判断されました」といった理由で求人紹介を受けられないこともあるんですね。
これは決してあなた自身に問題があるというわけではなく、dodaチャレンジの仕組み上、対応が難しいと判断されたというケースです。
どのような状況が対象外とされやすいのかを知っておくことで、別のサービスの活用や、準備の方向性も見えてくるかもしれません。
障がい者手帳を持っていない場合(障がい者雇用枠」での求人紹介は、原則手帳が必要)
dodaチャレンジで紹介される求人の多くは「障がい者雇用枠」での募集です。
そのため、基本的には「障がい者手帳の保持」が応募の前提条件となっています。
手帳がない場合、そもそもエントリー対象外となってしまうため、求人の紹介自体が難しくなってしまうのです。
「精神障害者保健福祉手帳」や「身体障害者手帳」など、該当する可能性がある方は、まず手帳取得の手続きを検討してみることも大切です。
地域の医療機関や相談支援事業所で相談に乗ってもらえる場合もあります。
長期間のブランクがあって、職務経験がほとんどない場合
dodaチャレンジは「転職支援サービス」であるため、ある程度の職務経験があることが前提とされている傾向があります。
長期間のブランクがある方や、これまで働いた経験がほとんどないという場合、「すぐに求人紹介ができる状態ではない」と判断されてしまうこともあります。
とはいえ、希望がないわけではありません。
その場合は、まずは就労に向けた準備を整えることを目的とした「就労移行支援」などの福祉サービスを活用し、段階的にステップアップしていく道もあります。
焦らず、今できることから少しずつ積み重ねていきましょう。
状が不安定で、就労が難しいと判断される場合(まずは就労移行支援を案内されることがある)
dodaチャレンジでは、就労に向けた意欲やスキルも大切ですが、何よりも「安定して働き続けられるかどうか」という視点を重視しています。
そのため、現在の健康状態や生活のリズムが大きく崩れていたり、医療的なフォローがまだ必要な段階であると判断された場合には、まずは「就労移行支援」などの福祉サービスの利用を案内されることもあります。
これは遠回りのように感じるかもしれませんが、長く安心して働き続けるための大切な準備期間とも言えるのです。
今は少し立ち止まって、自分のペースで土台を整えることも一つの選択肢ですよ。
断られる理由3・面談での印象・準備不足が影響する場合
dodaチャレンジのような転職エージェントでは、面談を通して求職者の状況や希望をヒアリングし、求人とのマッチングを行います。
その面談時の印象や準備状況が、紹介の可否に大きく影響することがあるんです。
「うまく話せなかった」「何を伝えれば良いのか分からなかった」という不安を感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
少しの準備や考えの整理によって、印象がグッと良くなり、紹介の可能性が広がることもあります。
自分を責めるのではなく、「伝える練習」をしていくことが大切です。
障がい内容や配慮事項が説明できない
自分の障がいについて説明するのは、とても勇気がいることですし、難しいと感じる方も多いですよね。
しかし、dodaチャレンジでは企業とのマッチングを行う上で、必要な配慮や特性を把握することが欠かせません。
「どんな環境なら働きやすいか」「どんな配慮が必要か」といったことを、自分なりに整理して伝えられるようにしておくと、エージェント側も適切なサポートをしやすくなります。
最初はうまく伝えられなくても、少しずつ言葉にできるようになるだけでも前進です。
どんな仕事をしたいか、ビジョンが曖昧
「とにかく働きたい」という気持ちが先に立ってしまって、何をしたいのか明確に伝えられないという方も多いかもしれません。
でも、エージェント側は希望の方向性が見えないと、紹介先を選ぶことが難しくなってしまいます。
「できれば事務系で…」というぼんやりした希望ではなく、「人と関わる仕事が好き」「ルーティン業務が得意」といった自分の傾向を言語化しておくことがポイントです。
難しく考えすぎず、まずは「どんな働き方が心地よいか」から考えてみると、自然とビジョンもクリアになっていきます。
職務経歴がうまく伝わらない
これまでの職務経歴やアルバイト経験をうまく言葉にできず、面談で苦労する方も少なくありません。
「自分なんて大した経験ないし…」と感じている方ほど、そのままになってしまいがちです。
でも、どんな経験も、視点を変えることでしっかりとアピールポイントになります。
例えば、長く働き続けた経験や、人と協力して進めた仕事なども立派な実績です。
職務経歴は過去の話ですが、それをどう伝えるかが未来を左右するカギになるんです。
事前に話す内容を紙にまとめておくだけでも、自信を持って面談に臨めるようになりますよ。
断られる理由4・地方エリアやリモート希望で求人が少ない
「求人は全国対応」と聞くと、どこに住んでいても仕事が紹介されるように思えますが、現実は少し違います。
dodaチャレンジでももちろん全国対応をしていますが、実際の求人数には地域差があるのが実情です。
特に地方にお住まいの方や、完全リモート勤務を希望する方にとっては、紹介可能な求人がぐっと限られてしまうケースも多いです。
「どうして求人がないのだろう…」と悩むよりも、まずはその背景を知ることで、柔軟な選択肢を見つける手助けになるかもしれません。
地方在住(特に北海道・東北・四国・九州など)
都市部と比べて、地方エリアでは企業数自体が少なく、障害者雇用を積極的に行っている企業も限られています。
北海道や東北、四国、九州といったエリアでは、dodaチャレンジが取り扱っている求人の中でもかなり絞られてしまうため、紹介が難しくなることがあります。
これは個人の問題ではなく「そもそも求人が存在していない」ことが多いんです。
こういった場合には、地元密着型の転職支援サービスを併用したり、広域通勤を視野に入れるなど、少しだけ柔軟に対応することで道が開けることもありますよ。
完全在宅勤務のみを希望している場合(dodaチャレンジは全国対応ではあるが地方によっては求人がかなり限定される)
在宅勤務の需要が高まってきたとはいえ、完全在宅の求人はまだまだ少数派です。
特にdodaチャレンジのような障害者雇用枠では、勤務環境の配慮が求められることも多いため、実際には「一部在宅可」「週数回出社あり」といった求人が主流です。
「絶対に出社NG」「フルリモート限定」という条件を設定してしまうと、マッチする求人が極端に減ってしまい、結果的に紹介が難しくなることもあります。
もちろん理想の働き方を大切にすることも必要ですが、少しだけ柔軟な視点を持つことで、可能性を広げられる場合もあります。
断られる理由5・登録情報に不備・虚偽がある場合
dodaチャレンジでは、登録情報をもとに面談や求人紹介が進んでいきます。
そのため、情報に不備があったり、誤解を招くような内容があると、エージェント側で「紹介が難しい」と判断されてしまうことがあります。
特に意図せず事実と異なる内容を記載してしまった場合でも、それが「虚偽」とみなされる可能性もあるため注意が必要です。
無理に良く見せようとするよりも、ありのままの情報を正直に伝える方が、結果的に良いご縁に繋がることが多いんです。
手帳未取得なのに「取得済み」と記載してしまった
「今後取得予定だから…」という軽い気持ちで、まだ持っていない障害者手帳を「取得済み」としてしまうと、dodaチャレンジ側では紹介を進めることができません。
障害者雇用枠の求人は、実際に手帳を保持していることが応募の前提条件となるため、取得前の段階では「手帳申請中」など、正確な情報を記載することが大切です。
早く求人を見たい気持ちも分かりますが、焦らず、正しいステップを踏むことで信頼関係も築きやすくなりますよ。
働ける状況ではないのに、無理に登録してしまった
就職への意欲はあるけれど、実際には体調が不安定で働く準備が整っていないというケースも少なくありません。
その状態で登録してしまうと、面談時に「まだ就労には早いかもしれません」と判断され、求人紹介を断られてしまう可能性もあるんです。
これは冷たく突き放すという意味ではなく、今は無理せず「準備期間」として他の支援を活用した方が良いという配慮でもあります。
自分を責める必要はありません。
まずは心と体を整えるところから始めましょう。
職歴や経歴に偽りがある場合
意図的であれ無意識であれ、経歴に事実と異なる内容が含まれていると、dodaチャレンジでは信頼性に関わる大きな問題とされます。
「バレないだろう」と思って記載した内容も、面談や企業とのやり取りの中で矛盾が生まれることがあります。
エージェント側も、信頼をもとにサポートを行っているため、事実と異なる情報は双方にとってリスクとなってしまうんですね。
自分のこれまでの経歴に自信が持てなくても、正直に伝えた上で「これからどうしていきたいか」に目を向けることが、前向きなスタートになるはずです。
断られる理由6・企業側から断られるケースも「dodaチャレンジで断られた」と感じる
「dodaチャレンジから断られた」と感じてしまう方の中には、実は企業側の選考で不採用となったケースも含まれています。
これは、dodaチャレンジ自体が断ったというよりも、紹介した企業での選考結果として「お見送り」となったという状況です。
もちろん、結果的にご縁がなかったという事実は変わりませんが、エージェント側としては最大限のマッチングを行った上での判断であることが多いです。
不採用はあくまでも「相性やタイミングによるもの」と考えて、落ち込まずに次のチャンスを探していくことが大切です。
不採用は企業の選考基準によるもの
企業の採用判断は、スキルや経験だけでなく、社風との相性や組織内のタイミングなど、さまざまな要素が絡んでいます。
たとえ十分なスキルがあっても、「今は他の候補者がよりマッチしていた」という理由で不採用になることもあるんですね。
このような場合、dodaチャレンジ側は紹介の段階までしっかりと対応してくれていることがほとんどです。
「dodaチャレンジに登録しても意味がなかった」と捉えるのではなく、自分に合う企業と出会うまでの通過点と捉えて、前向きに次の一歩を踏み出していきましょう。
dodaチャレンジで断られた人の体験談/どうして断られたのか体験談や口コミを調査しました
実際にdodaチャレンジで「断られた」と感じた方たちの体験談をもとに、どのような理由があるのかをよりリアルに知ることができます。
一人ひとりの背景や希望が異なる中で、どこにズレがあったのか、どんな対応をされたのかを知ることは、今後の行動を考えるうえでとても参考になるはずです。
同じような悩みや体験を持つ方の声を通じて、自分の現状と照らし合わせながら、対策や改善のヒントを見つけていただけたら嬉しいです。
体験談1・障がい者手帳は持っていましたが、これまでの職歴は軽作業の派遣だけ。PCスキルもタイピング程度しかなく、特に資格もありません。紹介できる求人がないと言われてしまいました
この方のように、障がい者手帳を持っていたとしても、職務経験やスキルの点でマッチングが難しいと判断されることがあります。
特にdodaチャレンジでは事務系やオフィスワークの求人が中心となっているため、ある程度のPCスキルや職歴が求められる傾向があります。
ただし、これは一時的な結果に過ぎません。
今からスキルを磨いていくことで、未来の選択肢は大きく変わっていきます。
焦らず、一歩ずつ準備をしていくことが大切です。
体験談2・継続就労できる状態が確認できないため、まずは就労移行支援などで安定した就労訓練を』と言われてしまいました。
「働きたい」という気持ちはあっても、エージェントは「継続して働き続けられるかどうか」という視点を重視しています。
この体験談のように、現在の体調や生活の安定性が確認できない場合には、まずは就労移行支援などの福祉サービスを提案されることがあります。
一見遠回りのように感じるかもしれませんが、自分のペースで就労の土台を整えることが、長く安定して働ける未来への確かな一歩となるはずです。
体験談3・精神疾患で長期療養していたため、10年以上のブランクがありました。dodaチャレンジに相談したものの、『ブランクが長く、就労経験が直近にないため、まずは体調安定と職業訓練を優先しましょう』と提案されました
長期療養やブランクがあると、どうしても就職活動では不安要素として見られてしまうことがあります。
この方のように、エージェント側から「まずは準備期間を大切にしましょう」と提案されることは、決して否定ではなく「いま無理をしてほしくない」という配慮の現れでもあります。
焦る気持ちをぐっとこらえて、まずは体調を整えることに集中する。
それが回り道に見えて、実は一番の近道だったりするんです。
体験談4・四国の田舎町に住んでいて、製造や軽作業ではなく、在宅でのライターやデザインの仕事を希望していました。dodaチャレンジからは『ご希望に沿う求人はご紹介できません』といわれました
地方在住で、さらに職種も専門的なものを希望している場合、マッチする求人が非常に少なくなることがあります。
この方のように、ライターやデザインなどの在宅ワークは人気が高く、求人数も限られているため、希望通りに紹介されることが難しいのが現実です。
こうしたケースでは、dodaチャレンジだけでなく、クラウドソーシングや業務委託の求人サイトなど、他のルートも併せて活用してみるのがおすすめです。
視野を広げることで、思いがけないチャンスが見えてくるかもしれません。
体験談5・これまでアルバイトや短期派遣での経験ばかりで、正社員経験はゼロ。dodaチャレンジに登録したら、『現時点では正社員求人の紹介は難しいです』と言われました
この方のように、これまでのキャリアがアルバイトや短期派遣に偏っている場合、正社員求人とのマッチングが難しいと判断されることがあります。
dodaチャレンジでは、企業側が正社員としての雇用を前提にしていることも多く、ある程度の職歴や継続就労経験を求められる傾向があります。
ただ、正社員経験がゼロだからといって諦める必要はありません。
契約社員や紹介予定派遣など、まずは「働く実績を積める形」から始めることで、将来的に正社員を目指す道も見えてきますよ。
体験談6・子育て中なので、完全在宅で週3勤務、時短勤務、かつ事務職で年収300万円以上という条件を出しました。『ご希望条件のすべてを満たす求人は現状ご紹介が難しいです』と言われ、紹介を断られました
子育てや家庭との両立を考えると、働き方に柔軟性を求めるのは当然のことです。
この方のように、在宅・時短・週3勤務・年収希望など、希望条件が多岐にわたる場合、それらすべてを満たす求人はどうしても限られてしまいます。
dodaチャレンジとしても、理想に合う求人が存在しない場合には正直に伝えることしかできません。
そんな時は、条件の中で「何が最優先なのか」を見直してみるのもひとつの方法です。
一部の希望をゆるめてみることで、意外なチャンスが舞い込むこともあるんです。
体験談7・精神障がい(うつ病)の診断を受けていますが、障がい者手帳はまだ取得していませんでした。dodaチャレンジに登録を試みたところ、『障がい者手帳がない場合は求人紹介が難しい』と言われました
精神疾患の診断を受けていても、障がい者手帳をまだ取得していない場合、dodaチャレンジでの求人紹介は難しくなってしまいます。
これはエージェント側の対応というよりも、企業の応募条件として「障がい者手帳の提示」が義務付けられているためなんですね。
「手帳の取得はハードルが高い…」と感じてしまう方も多いですが、実際には取得することで受けられる支援も増えるため、まずは地域の専門機関などに相談してみることをおすすめします。
一歩踏み出すことで、新しい選択肢が広がるかもしれません。
体験談8・長年、軽作業をしてきたけど、体調を考えて在宅のITエンジニア職に挑戦したいと思い、dodaチャレンジに相談しました。『未経験からエンジニア職はご紹介が難しいです』と言われ、求人は紹介されませんでした
新しい分野に挑戦したいという前向きな気持ちは素晴らしいことです。
でも、ITエンジニア職のような専門性の高い仕事は、未経験での採用ハードルが非常に高いのが現実です。
この方のように、「これから学んで挑戦したい」という意欲があっても、現時点でのスキルが不足している場合は、dodaチャレンジでは求人紹介が難しくなってしまいます。
まずは基礎的なスキルを独学やスクールで学び、ポートフォリオを作成するなど準備を進めることで、チャンスが近づいてくることもありますよ。
体験談9・身体障がいで通勤も困難な状況で、週5フルタイムは無理。短時間の在宅勤務を希望しましたが、『現在ご紹介できる求人がありません』と断られました
通勤が難しい方にとって、在宅勤務はとても重要な条件ですよね。
この方のように、身体的な事情から短時間かつ在宅勤務を希望される場合、求人の選択肢がかなり限定されてしまいます。
dodaチャレンジが取り扱っている求人の中には、フルタイムや出社前提のものが多いため、マッチングが難しくなることも少なくありません。
ただ、今後は在宅や短時間勤務のニーズも増えていく傾向にあるため、他のサービスも含めて広く情報収集をしていくことで、道が開けるかもしれません。
体験談10・前職は中堅企業の一般職だったけど、今回は障がい者雇用で管理職や年収600万以上を希望しました。dodaチャレンジでは『ご紹介可能な求人は現在ありません』と言われました
高収入や管理職を目指すことは、キャリアアップの一環として当然の目標です。
ただし、障がい者雇用枠では、まだまだ高年収層や管理職クラスの求人が少ないのが現状です。
この方のように、スキルや実績があっても、それに見合う求人がdodaチャレンジの中で見つからなければ、紹介は難しくなってしまいます。
そんなときは、一般枠での転職も視野に入れたり、自身の強みを活かせる業界を再検討するなど、柔軟なアプローチが求められます。
未来は今の選択次第で、いくらでも広がっていくものですよ。
dodaチャレンジで断られたときの詳しい対処法について紹介します
dodaチャレンジで「紹介が難しい」と言われたとき、落ち込んでしまうのは当然のこと。
でも、それがゴールではなく、次に進むためのきっかけに変えることもできるんです。
大切なのは「自分に足りなかったものは何か」「今からできることは何か」を見つめ直すこと。
ここでは、断られた理由別に、具体的な対処法や改善のステップを紹介していきます。
ちょっとした工夫や行動の積み重ねで、また新しい扉が開いていくかもしれませんよ。
スキル不足・職歴不足で断られたとき(職歴が浅い、軽作業や短期バイトの経験しかない、PCスキルに自信がないなど)の対処法について
「これまでアルバイトばかりだった…」「PCはタイピングしかできないかも…」といった不安を抱えている方も多いですよね。
でも安心してください。
スキルや職歴は、後から身につけることが十分に可能です。
重要なのは、「今、自分にできることから一歩ずつ始める」ことです。
スキルや知識は武器になりますし、それを身につけようとする姿勢自体が、今後の転職活動にもプラスに働きます。
ここでは、今すぐにでも始められる対処法をいくつか紹介していきますね。
ハローワークの職業訓練を利用する/ 無料または低額でPCスキル(Word・Excel・データ入力など)が学べる
ハローワークが実施している職業訓練は、無料または非常に低額で受けられるものが多く、求職者にとってとてもありがたい制度です。
特に、WordやExcel、データ入力といった事務系に必要なPCスキルは、多くの職業訓練で学ぶことができます。
これまで触ったことがないという方でも、基礎から丁寧に教えてくれるコースが充実していますし、修了後にはスキルの証明にもなります。
スキルアップと自信の獲得、そして次のステップへ進むための第一歩として、とてもおすすめできる選択肢ですよ。
就労移行支援を活用する/実践的なビジネススキル、ビジネスマナー、メンタルサポートも受けられる
「働くことに不安がある」「ブランクが長くて自信がない」という方にとって、就労移行支援は非常に心強いサポートです。
ここでは、単なるスキル学習だけでなく、職場で必要なビジネスマナーや報連相のトレーニング、さらにはメンタルサポートまで幅広く受けることができます。
事業所によっては、職場実習の機会もあり、実践的な経験を積むことも可能です。
「いきなり就職は不安…」という方は、まずはここで自分のペースを取り戻しながら、働くための土台をしっかり作っていきましょう。
資格を取る/MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級があると、求人紹介の幅が広がる
「何かひとつ、アピールできる武器が欲しい」という方におすすめなのが、資格の取得です。
中でも、MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級は、dodaチャレンジで紹介される事務系の求人との相性が良く、スキル証明として非常に有効です。
これらの資格は独学でも十分に合格可能ですし、通信講座やハローワークの職業訓練で学べることもあります。
履歴書にも書けるので、自信にもつながりますよ。
「学ぶことで未来が開ける」ことを、ぜひ体感してみてください。
ブランクが長すぎてサポート対象外になったとき(働くことへの不安が強い、数年以上の離職や療養機関があるなど)の対処法について
ブランクがあることで「もう働けないのでは…」と感じる方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。
大切なのは、「今からどうやって一歩を踏み出すか」です。
dodaチャレンジでは、ブランクが長いと就労準備が整っていないと判断されることがありますが、それは「今は焦らず整える時間を持ちましょう」という、あくまで前向きな提案でもあります。
ここでは、ブランクが長い方向けに、無理なく社会復帰につながる対処法をご紹介していきます。
就労移行支援を利用して就労訓練をする/毎日通所することで生活リズムを整え、安定した就労実績を作れる
ブランクが長い方にとって、まず整えるべきは「生活リズム」です。
就労移行支援では、毎日の通所を通じて体調を整えながら、ビジネスマナーやPCスキルのトレーニングを受けることができます。
「通うことができた」という実績自体が、再就職への自信につながるんです。
また、就労移行支援事業所によっては、企業との実習や模擬面接の機会もあり、実践的なステップアップが可能になります。
焦らず着実に、「働くための準備」を整えていきましょう。
短時間のバイトや在宅ワークで「実績」を作る/週1〜2の短時間勤務から始めて、「継続勤務できる」証明をつくる
いきなりフルタイムで働くことに不安があるなら、まずは週に1〜2回、数時間だけの短時間バイトや在宅ワークから始めてみるのも効果的です。
「働ける状態です」と口で説明するよりも、実際に働いてみた経験こそが、一番の説得力になります。
「継続して勤務できた」という実績を作ることで、次回のdodaチャレンジの登録時にもポジティブな材料として評価されやすくなります。
焦らなくて大丈夫。
まずは“できることから始める”ことが一番大切です。
実習やトライアル雇用に参加する/企業実習での実績を積むと、再登録時にアピール材料になる
ハローワークや就労移行支援、地域の福祉機関を通じて参加できる「職場実習」や「トライアル雇用」は、ブランクのある方にとって非常に有効な選択肢です。
短期間でも企業の中で働く経験を持つことで、「現場に慣れる力」や「仕事に対する姿勢」を実感として学ぶことができますし、その実績が後々の転職活動でのアピール材料にもなります。
再びdodaチャレンジに登録する際にも、「こんな実習を経験しました」と伝えられたら、それだけで印象はぐっと良くなりますよ。
地方在住で求人紹介がなかったとき(通勤できる距離に求人が少ない、フルリモート勤務を希望しているなど)の対処法について
地方にお住まいの方の中には、「そもそも求人が全然ない…」と感じることがあるかもしれません。
dodaチャレンジでは全国対応をうたっていますが、実際のところ、都市部と比べて地方の求人数は限られているのが現実です。
だからこそ、少し視点を広げたり、他のサービスをうまく活用することが鍵になってきます。
ここでは、地方在住の方が今すぐできる行動や、求人を増やすための工夫をご紹介します。
在宅勤務OKの求人を探す/他の障がい者専門エージェント(atGP在宅ワーク、サーナ、ミラトレ)を併用
地方に住んでいて、通勤が難しい場合は「在宅勤務可」の求人に的を絞って探してみましょう。
dodaチャレンジ以外にも、在宅勤務に強い障がい者専門の転職エージェントが存在します。
たとえば「atGP在宅ワーク」や「サーナ」「ミラトレ」などがその代表です。
複数のエージェントを併用することで、自分に合う求人に出会える確率も高まりますし、それぞれのエージェントの得意分野も違うため、情報の幅も広がっていきますよ。
クラウドソーシングで実績を作る/ランサーズ、クラウドワークスなどでライティングやデータ入力の仕事を開始
在宅でできる仕事として、クラウドソーシングの活用もとても有効です。
「ランサーズ」や「クラウドワークス」などのサイトでは、ライティングやデータ入力、簡単なアンケート作業など、スキルに応じた仕事を選ぶことができます。
こうした仕事を通じて「自宅で仕事ができる力」を証明することができれば、今後の求人紹介や企業選考でも好印象につながる可能性があります。
最初は小さな案件からで構いません。
少しずつ“実績”を積み重ねていきましょう。
地域の障がい者就労支援センターやハローワークに相談する/地元密着型の求人情報が得られる場合がある
地方での就職活動では、地元の就労支援機関やハローワークの活用がとても重要です。
地域の実情をよく知っているスタッフが在籍しており、ネットには出ていない「非公開求人」や、地元密着の中小企業の情報を紹介してくれることもあります。
また、通所型の支援を通じてスキルアップができたり、企業見学や実習の機会を得られることもあります。
自分ひとりで抱え込まず、まずは「相談すること」から始めてみてください。
道は、そこからきっと開けていきます。
希望条件が厳しすぎて紹介を断られたとき(完全在宅・週3勤務・年収◯万円など、条件が多いなど)の対処法について
「絶対に在宅がいい」「週3日までしか働けない」「年収は○○万円以上じゃないと…」といったように、希望条件が多くなると、どうしてもマッチする求人が少なくなってしまいますよね。
自分の理想を叶えたい気持ちはとても大切ですし、それを諦めろとは言いません。
でも、一旦立ち止まって、「その条件、本当に全部が絶対必要?」と見直してみると、思いがけず新しい道が見えてくることもあります。
ここでは、条件が厳しいときに試してみたい、現実的な対処法をお伝えしていきますね。
条件に優先順位をつける/「絶対譲れない条件」と「できれば希望」を切り分ける
まずは、すべての条件を一度紙に書き出してみてください。
そして、「絶対に外せないもの」と「叶えば嬉しいな、くらいの希望」に分けてみるんです。
たとえば、「在宅勤務」は譲れないけれど、「週3勤務」は実は週4までならOKかも…という気づきがあるかもしれません。
優先順位を明確にしておくことで、エージェント側もマッチングしやすくなり、より現実的な求人提案につながっていきますよ。
譲歩できる条件はアドバイザーに再提示する/ 勤務時間、出社頻度、勤務地を柔軟に見直す
一度提示した条件で断られてしまったとしても、「条件を見直しました」と伝えることで再提案をしてもらえる可能性があります。
例えば「週3勤務→週4までOK」「完全在宅→週1出社でも大丈夫」「年収〇〇万円→最低〇〇万円でも検討可」といった形で、柔軟な姿勢を見せると、エージェント側も「この人なら紹介できる求人があるかも」と前向きに対応してくれることが多いです。
条件の見直しは、希望を下げることではなく、現実に一歩近づくための前向きな戦略なんです。
段階的にキャリアアップする戦略を立てる/最初は条件を緩めてスタート→スキルUPして理想の働き方を目指す
いきなり理想の条件をすべて満たす仕事を探すのではなく、「まずは一歩手前からスタートする」という戦略もとても有効です。
たとえば、最初は週5出社でも、自分のスキルが認められて在宅勤務に切り替わるケースもありますし、年収も実績次第でアップしていくことは十分にあり得ます。
「段階的にステップアップしていけばいい」と考えることで、無理のない形で希望に近づいていけるはずです。
理想を捨てる必要はありません。
今はその準備段階なのかもしれませんね。
手帳未取得・障がい区分で断られたとき(障がい者手帳がない、精神障がいや発達障がいで手帳取得が難航している、支援区分が違うなど)の対処法について
障がい者雇用を前提とするdodaチャレンジでは、「障がい者手帳の取得」が求人紹介の前提条件となっているため、まだ手帳を持っていない方にとっては壁のように感じられることもあります。
でも、手帳がない=働けないというわけではありません。
状況によっては、他の支援策や選択肢もありますし、時間をかけて手帳を取得することで未来の幅が大きく広がることもあります。
ここでは、そんなときに取るべき行動を、いくつか紹介していきますね。
主治医や自治体に手帳申請を相談する/ 精神障がい・発達障がいも条件が合えば取得できる
「自分は手帳を取れるのか分からない」という方も多いと思います。
そんなときは、まずは主治医に相談してみるのが第一歩です。
精神障がいや発達障がいでも、症状や通院歴、診断書の内容によっては手帳取得が可能です。
自治体の福祉窓口でも詳しい情報が得られますので、ひとりで悩まず相談してみてくださいね。
手帳があることで、雇用面だけでなく、医療費助成や福祉サービスなど多くのメリットが得られることもありますよ。
就労移行支援やハローワークで「手帳なしOK求人」を探す/一般枠での就職活動や、就労移行後にdodaチャレンジに戻る
手帳がない状態でも働ける場はあります。
たとえばハローワークや一部の就労移行支援事業所では、手帳がなくても受け入れてくれる求人や訓練先があります。
また、一般枠での就職活動を視野に入れて、少しずつ実績を積み重ねていく方法もあります。
一度dodaチャレンジの対象外となってしまっても、あとで再登録が可能になるケースも多いので、まずは「今できること」から着実に進めていきましょう。
医師と相談して、体調管理や治療を優先する/手帳取得後に再度登録・相談する
今すぐの就職よりも、まずは体調の安定を優先すべきタイミングということもあります。
そんなときは無理をせず、主治医と相談しながら治療や日常生活のリズムを整えることに集中してみてください。
落ち着いてきたら、改めて手帳の取得を検討し、再びdodaチャレンジに登録するという流れも、決して遅くはありません。
一見遠回りに見えても、それが結果的に一番の近道になることもあるんです。
その他の対処法/dodaチャレンジ以外のサービスを利用する
dodaチャレンジはとても心強いサポートではありますが、「ここでダメだったから終わり」ではありません。
実は、障がい者雇用をサポートするサービスはたくさん存在していて、それぞれに得意な分野や求人の特徴があります。
たとえば、在宅ワークに強いエージェントや、就労移行に力を入れている事業所、一般枠でのキャリア支援をしているところなど、視点を少し変えるだけで新しい選択肢が見えてくることもあります。
自分に合う場所がきっとあるはずなので、どうか諦めないでくださいね。
dodaチャレンジで断られた!?発達障害や精神障害だと紹介は難しいのかについて解説します
「精神障害や発達障害があると、dodaチャレンジでは求人を紹介してもらえないのでは?」そんな不安を感じたことはありませんか?実際、インターネット上には「紹介されなかった」という声もありますが、それにはさまざまな理由があるんです。
障がいの種類や特性によって、マッチする求人の傾向が異なることは確かですが、それは「働けない」ことを意味しているわけではありません。
今回は、特に身体障害者手帳を持っている方の就職事情からスタートして、なぜ紹介の可否に差が出るのかについて、背景をやさしく解説していきます。
身体障害者手帳の人の就職事情について
身体障がいのある方にとって、dodaチャレンジなどの障がい者向け転職サービスは比較的求人のマッチングがしやすい傾向があります。
これは、身体障がいの場合、企業側が配慮すべき点を具体的にイメージしやすく、採用判断がしやすいためです。
また、支援機関や行政も物理的なサポートに強みを持っているため、就職までのサポート体制も整っている場合が多いです。
この章では、そんな身体障がいを持つ方々の就職の特徴や、企業がどのように対応しているかを紹介していきます。
障害の等級が低い場合は就職がしやすい
身体障害者手帳の等級が比較的軽度である場合、就職先の選択肢が広がる傾向にあります。
これは、通勤や業務において特別な配慮が少なくて済むため、企業側も受け入れやすいと感じるからです。
もちろん、障害の程度によって支援内容は変わりますが、「できることが多い」と判断されることが、求人紹介においてプラスに働くケースが多いのです。
ただし、これはあくまで一般論であり、「等級が高いから就職できない」ということでは決してありません。
重要なのは、自分の特性を正しく伝え、配慮の希望を明確にすることなんです。
身体障がいのある人は、障がいの内容が「見えやすい」ことから、企業側も配慮しやすく採用しやすい傾向にある
身体障がいの場合、たとえば車椅子の使用や、聴覚・視覚の支援が必要など、「配慮すべきポイント」が視覚的に明確であることが多いです。
企業側にとっても、何をすれば働きやすい環境になるのかが想像しやすく、設備面の整備や業務内容の調整など、現実的な対応を取りやすいんですね。
これにより「採用しても大丈夫そう」と企業が安心できるため、マッチングの成功率が高くなる傾向があります。
見えにくい障がいと比べると、良くも悪くも「誤解されにくい」というのが大きなポイントです。
企業側が合理的配慮が明確にしやすい(例:バリアフリー化、業務制限など)から、企業も安心して採用できる
企業が障がい者を採用する際には「合理的配慮」が法律で求められています。
身体障がいの場合、この配慮が具体的で実施しやすいケースが多いんです。
たとえば、「段差をなくす」「トイレをバリアフリーにする」「重いものを持たない業務にする」といったように、明確な対応策がとれるんですね。
この“分かりやすさ”が、企業側にとっての安心感にもつながり、「採用後のトラブルが少なそう」と感じてもらいやすくなります。
結果として、身体障がいの方は就職においてやや有利になるケースがあるのです。
上肢・下肢の障がいで通勤・作業に制約があると求人が限られる
上肢や下肢に障がいがある方の場合、通勤や業務そのものに制約が出てしまうことがあり、希望できる求人が限られてしまう傾向にあります。
たとえば階段のある職場、長距離の移動が必要な現場作業、立ちっぱなしの仕事などは物理的に難しいこともありますよね。
ただ、そんな中でも「在宅勤務可能」や「座ってできるデスクワーク」「バリアフリー環境の整った企業」など、選択肢は確実に存在します。
大切なのは、「できないこと」ではなく「できること」に焦点を当てて、応募先との相性を見極めることなんです。
コミュニケーションに問題がない場合は一般職種への採用も多い
身体障がいがあっても、コミュニケーション能力に問題がなければ、一般の職種での採用のチャンスはしっかりあります。
企業はチームでの連携や報連相がスムーズにできるかどうかを重視しているため、たとえば事務、営業アシスタント、コールセンターなどの業務に向いていると判断されることも多いです。
「体は少し不自由だけど、伝える力はある」ということをうまくアピールできれば、十分に戦力として認められやすいのです。
障がいのあるなしに関わらず、対話力はどの職場でも求められる重要な要素ですよ。
PC業務・事務職は特に求人が多い
身体障がいのある方に人気で、かつ企業からの求人が多いのがPCを使った事務系の仕事です。
データ入力、資料作成、請求書の発行など、比較的決まった業務をこなす職種は、働く側にとっても業務を習得しやすく、企業にとっても採用しやすい傾向にあります。
また、多くの企業では、障がい者雇用を進める中で、こうした事務職の受け入れ体制を整えている場合が多く、設備面でも比較的安心できる職場環境が用意されていることも。
PCスキルに自信がある方には、まずはこの分野からのスタートをおすすめしたいです。
精神障害者保健福祉手帳の人の就職事情について
精神障がいを抱える方にとって、就職活動は不安との戦いでもあると思います。
「採用されても続けられるのかな」「面接でどう伝えたらいいんだろう」と、悩むのも当然です。
実際、精神障害者保健福祉手帳を持っている方は、求人の紹介に際して「症状の安定性」「職場での配慮の必要性」など、細かなヒアリングをされるケースが多いです。
ただし、それはネガティブな意味ではなく、“無理なく続けて働ける職場かどうか”を一緒に探すためのプロセスでもあります。
今回は、そんな精神障がいのある方の就職事情について、安心して向き合えるように分かりやすくお伝えしていきますね。
症状の安定性や職場での継続勤務のしやすさが重視される
精神障がいのある方が求人を紹介してもらう際、一番大きなポイントとして見られるのが「症状の安定性」です。
どんなにスキルがあっても、体調が不安定で欠勤が続いてしまうと、仕事が継続しにくくなってしまいますよね。
そのため、「定期的に通院できているか」「服薬の管理ができているか」「日中の活動リズムは安定しているか」といった点がチェックされることが多いです。
これらがクリアできていることで、エージェント側も自信をもって求人を紹介できるようになるんです。
見えにくい障がいなので、企業が「採用後の対応」に不安を持ちやすいのが現実
精神障がいは外見からは分かりにくいため、企業側が「何を配慮すればいいのか分からない」と感じてしまうことが少なくありません。
その結果、「採用したけれど、対応できるか不安」と感じ、慎重になってしまう企業もあります。
これはとてももどかしいことではありますが、見えにくいからこそ「説明の仕方」や「伝え方」がとても重要になります。
適切な配慮をしてもらうためにも、自分から「私はこういう点を気をつけています」と伝えられるように準備しておくと安心ですよ。
採用面接での配慮事項の伝え方がとても大切!
精神障がいがある方が面接で意識すべきことのひとつが、「配慮事項を明確に伝える」ことです。
たとえば、「週に一度、通院のため午後は早退します」「電話対応は苦手なので、業務に含まれない部署を希望します」といった形で、具体的に伝えることで、企業側も「この方に必要な配慮はこれなんだな」と理解しやすくなります。
遠慮して何も言わずに入社してしまうと、お互いにストレスを感じる原因になりやすいので、誠実に、でも前向きに伝えることが、安心して働く第一歩になります。
療育手帳(知的障害者手帳)の人の就職事情について
療育手帳をお持ちの方の就職活動は、障がいの程度やサポート体制によって、大きく可能性が変わってくることがあります。
特に、就労先が一般企業なのか、福祉的な就労支援事業所なのかは、療育手帳の判定区分によって分かれてくる傾向があります。
とはいえ、一人ひとりの強みや個性をしっかり把握し、適切なサポートを受けながら進めれば、無理のない働き方に出会えることも多いです。
ここでは、A判定とB判定、それぞれの傾向についてやさしくお話ししていきます。
療育手帳の区分(A判定 or B判定)によって、就労の選択肢が変わる
療育手帳には「A判定(重度)」と「B判定(中軽度)」という区分があり、この違いが、就労先の選択肢に大きく影響します。
A判定の場合は、日常生活にも支援が必要なケースが多く、福祉サービスの活用が中心になることが多いです。
一方、B判定の方であれば、サポートを受けながら一般就労にチャレンジする人も増えています。
手帳の区分はあくまで目安であり、それだけで就職の可否が決まるわけではありませんが、自分に合った道を選ぶための参考にはなります。
A判定(重度)の場合、一般就労は難しく、福祉的就労(就労継続支援B型)が中心
A判定の方は、知的障がいの影響が日常生活や対人関係に強く出ることがあり、一般企業での就労はハードルが高いこともあります。
そのため、無理なく働ける場として「就労継続支援B型」などの福祉的就労を選択する方が多いです。
ここでは、作業量や時間が個別に調整できたり、生活支援とセットで就労訓練を受けられるなどのサポートが整っています。
無理せず、安心して働ける環境から少しずつステップアップしていく方法もありますよ。
B判定(中軽度)の場合、一般就労も視野に入りやすい
B判定の場合、日常生活がある程度自立できていて、支援があれば職場での就労も可能と判断されるケースが多いです。
そのため、就労移行支援を活用しながら一般企業を目指す方も多く、事務補助や軽作業などからスタートすることもあります。
ポイントは、「どんな配慮があれば働けるか」を自分の中で整理しておくこと。
そして、その内容をエージェントや面接先にきちんと伝えられる準備をしておくことで、就職への道が開けやすくなります。
障害の種類と就職難易度について
障がいの種類によって、就職のしやすさや支援の内容は大きく変わってくるのが現実です。
たとえば、身体障がいのように「見えやすい障がい」の場合は、企業側も配慮がしやすく、採用につながりやすいことがあります。
一方で、精神障がいや発達障がい、知的障がいといった「見えにくい障がい」では、配慮の内容が分かりづらく、企業が採用後の対応に不安を感じてしまうことも少なくありません。
でも、これは「就職できない」ことを意味しているわけではありません。
正しい情報を伝え、無理なく働ける職場を探すことで、誰にでも働ける可能性は広がっています。
「就職が難しい=自分に価値がない」なんて思わないでくださいね。
自分らしい働き方を見つけること、それがいちばん大切なことなんです。
| 手帳の種類 | 就職のしやすさ | 就職しやすい職種 | 難易度のポイント |
| 身体障害者手帳(軽度〜中度) | ★★★★★★ | 一般事務・IT系・経理・カスタマーサポート | 配慮事項が明確で採用企業が多い |
| 身体障害者手帳(重度) | ★★ | 軽作業・在宅勤務 | 通勤や作業負担によって求人が限定 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | ★★ | 事務補助・データ入力・清掃・在宅ワーク | 症状安定と継続勤務が評価されやすい |
| 療育手帳(B判定) | ★★★★ | 軽作業・事務補助・福祉施設内作業 | 指導・サポート体制が整った環境で定着しやすい |
| 療育手帳(A判定) | ★★ | 福祉的就労(A型・B型) | 一般就労は難しく、福祉就労が中心になる場合が多い |
障害者雇用枠と一般雇用枠の違いについて
就職活動をするうえで、障がいのある方が選ぶ選択肢のひとつに「障害者雇用枠」と「一般雇用枠」のどちらで応募するかという問題があります。
どちらにもメリット・デメリットがありますが、大切なのは「自分にとって無理のない働き方」ができる道を選ぶことなんです。
ここでは、それぞれの雇用枠の違いや特徴をわかりやすく整理してみました。
自分がどちらの枠で応募するべきか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
障害者雇用枠の特徴1・企業が法律に基づき設定している雇用枠
障害者雇用枠とは、企業が障害者雇用促進法に基づいて設けている特別な雇用枠のことです。
この枠で採用される場合、企業は障がいのある方が働きやすいように、業務内容や勤務時間などを配慮してくれるケースが多く、就労に対する不安を軽減できるという利点があります。
特に就職が初めての方や、ブランクがある方、配慮が必要な症状を抱えている方にとっては安心して働ける環境になりやすいですよ。
障害者雇用枠の特徴2・障害者雇用促進法により、民間企業は従業員の2.5%以上(2024年4月〜引き上げ)を障がい者として雇用するルールがある
2024年4月から法定雇用率が引き上げられ、民間企業は従業員の2.5%以上を障がい者として雇用する義務があります。
これにより、障害者雇用枠の求人も少しずつ増えてきています。
企業にとっても「障がい者雇用に積極的な姿勢を示すこと」は社会的責任の一部になっており、真剣に採用活動に取り組むところも増えています。
この制度があるおかげで、障がい者雇用枠での就職のハードルが少しずつ下がってきているのはうれしい変化ですね。
障害者雇用枠の特徴3・障害をオープンにし配慮事項を明確に伝えた上で雇用される
障害者雇用枠では、障がいの内容や配慮してほしいことをオープンにした上で採用されるため、入社後に「言いにくいことを我慢する」といったストレスが少なくなる傾向があります。
たとえば「通院のために月1回の早退が必要」「人混みや大きな音が苦手」など、自分の状態に合わせた働き方を相談しやすいのが特徴です。
その分、最初の面接や登録の際には、しっかりと自己理解を深めて「何に配慮が必要か」を伝える準備が大切になってきます。
一般雇用枠の特徴1・障害の有無を問わず、すべての応募者が同じ土俵で競う採用枠
一般雇用枠とは、障がいのある・なしに関係なく、全ての応募者が同じ条件で競い合う採用枠です。
企業側は障がいの有無ではなく、スキル・経験・人物面など総合的に評価して採用を決めます。
そのため、自己PRがしっかりできる方や、過去の職歴や実績を活かしたいという方にとっては、より多くの選択肢から仕事を選ぶことができます。
ただし、配慮を求める場合は、そのタイミングや伝え方を慎重に考える必要があるので注意が必要です。
一般雇用枠の特徴2・障害を開示するかは本人の自由(オープン就労 or クローズ就労)
一般雇用枠では、障がいの有無をあえて企業に伝えずに就職する「クローズ就労」も可能です。
これは「障がいを理由に不利に扱われたくない」と考える方に選ばれる方法ですが、その反面、必要な配慮を受けづらくなるというリスクもあります。
反対に、障がいがあることを開示しながら一般枠で就職する「オープン就労」を選ぶ人もいますが、企業によっては配慮体制が整っていない場合もあるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
一般雇用枠の特徴3・基本的に配慮や特別な措置はないのが前提
一般雇用枠では、原則として障がいへの配慮や特別な措置はありません。
そのため、障がいによって日常業務に支障が出る可能性がある場合は、働き続けることが難しくなってしまうこともあるんです。
ただし、近年では「合理的配慮」が法律で義務付けられたこともあり、企業によっては柔軟に対応してくれるケースも増えてきました。
とはいえ、それでも障害者雇用枠と比べると環境整備は限定的であることが多いため、選ぶ際は慎重に検討することが大切です。
年代別の障害者雇用率について/年代によって採用の難しさは違うのか
障がい者の就職事情は、年齢によっても違いが見られます。
たとえば若年層であれば、ポテンシャルを重視した求人や、未経験OKの採用枠が比較的多く、これからの成長を期待して採用されることも珍しくありません。
一方で、年齢が上がるにつれて、即戦力としての実績やスキルを求められる傾向が強まり、採用基準も少しずつ厳しくなるのが現実です。
ここでは、厚生労働省の障害者雇用状況報告(2023年版)をもとに、年代別の雇用動向について見ていきましょう。
障害者雇用状況報告(2023年版)を元に紹介します
2023年に公表された障害者雇用状況報告によると、20代〜30代の若年層における障がい者雇用率は年々増加傾向にあります。
これは、企業が将来性や長期的な育成を重視するようになった影響もあり、若年層の障がい者にとってはチャンスが広がっている状況です。
一方で、40代以降になると求人の数そのものが減り始め、特に50代〜60代では求人の選択肢がかなり限定されてきます。
ただし、スキルや専門知識を活かせる分野では年齢を問わず採用される例もあるため、「年齢=不利」と決めつける必要はありません。
大切なのは、自分に合ったポジションと働き方を見つけることなんです。
| 年代 | 割合(障害者全体の構成比) | 主な就業状況 |
| 20代 | 約20~25% | 初めての就職 or 転職が中心。
未経験OKの求人も多い |
| 30代 | 約25~30% | 安定就労を目指す転職が多い。
経験者採用が増える |
| 40代 | 約20~25% | 職歴次第で幅が広がるが、未経験は厳しめ |
| 50代 | 約10~15% | 雇用枠は減るが、特定業務や経験者枠で採用あり |
| 60代 | 約5% | 嘱託・再雇用・短時間勤務が中心 |
若年層(20〜30代)の雇用率は高く、求人数も多い
20〜30代の若年層は、障がいのあるなしに関わらず、企業にとって「将来の伸びしろ」や「育成枠」として見られやすく、採用されるチャンスが比較的高いのが特徴です。
特に障がい者雇用枠においては、未経験OKの求人や研修制度のある職場も多く、長期的に活躍してもらえる人材として期待されています。
また、デジタルスキルやPC操作に慣れている世代でもあるため、事務職や在宅業務などでもマッチする求人が見つかりやすいです。
若さを「未熟」と捉えるのではなく、「これから吸収できる力」として見てもらえることが多いので、自信をもって就職活動を進めてほしいです。
40代以降は「スキル・経験」がないと厳しくなる
40代を過ぎると、企業側は「即戦力として活躍してもらえるか」という視点で採用を考えることが増えてきます。
そのため、未経験分野へのチャレンジや、スキルがない状態での応募は通過しにくくなるのが現実です。
ただし、これまでの業務経験や専門知識がある方は、その経験が強みとして評価されるケースも少なくありません。
たとえば、経理・総務・接客などの実務経験がある場合は、それに関連する求人が見つかりやすくなります。
年齢による不利を補うためにも、「自分が企業にどんな価値を提供できるか」を明確にしておくことが大切です。
50代以上は「短時間勤務」「特定業務」などに限られることが多い
50代以上の就職活動になると、求人数がかなり限られてくるのが現実です。
特に、体力的な配慮や勤務時間の調整が必要な場合、「週2〜3日勤務」や「定型業務のみ」など、業務範囲が限定された求人に絞られることが多くなります。
ただし、最近では高齢者雇用を積極的に進める企業や、経験を活かしたアドバイザー的なポジションを用意している企業も増えてきています。
無理にフルタイムや高収入を狙うよりも、「働きやすさ」「体調とのバランス」を重視した働き方を探すことが、50代以降の就職活動を前向きに進める鍵になります。
dodaチャレンジなどの就活エージェントのサービスに年齢制限はある?
就職活動において「年齢って関係あるの?」と不安に思う方は少なくないですよね。
dodaチャレンジをはじめとする就職エージェントには、明確な年齢制限は設けられていません。
ただし、実際に求人紹介が多くなるのは、スキルや勤務可能時間のバランスが取れている「20代〜50代前半」までの方が多いのも事実です。
でも、だからといって「年齢=断られる」わけではないので安心してください。
自分に合ったサービスや求人を見つけるために、いくつかの支援先をうまく併用していくことがポイントです。
年齢制限はないが 実質的には「50代前半まで」がメインターゲット層
dodaチャレンジなど多くの障がい者専門エージェントでは、年齢制限はありません。
しかし、実際に紹介される求人の多くは「20代〜50代前半」向けに設計されているケースがほとんどです。
そのため、50代後半以上の方の場合は、「求人が少ない」と感じることもあります。
でも、そこで諦めるのではなく、「自分の年齢に合った働き方」を考えることが大切です。
短時間勤務や在宅ワークなど、条件を工夫することで紹介される求人の幅が広がることもあるので、まずは希望を柔軟にして相談してみてくださいね。
ハローワーク障がい者窓口や障がい者職業センター(独立行政法人)も併用するとよい
年齢が高くなればなるほど、「dodaチャレンジだけでは求人が見つからなかった…」という声も聞かれます。
そんなときにぜひ活用してほしいのが、ハローワークの障がい者窓口や、障がい者職業センターといった公的機関です。
これらの機関では、年齢にかかわらずきめ細かなサポートが受けられたり、地元の企業情報を提供してくれることもあります。
特に、50代以上の方にとっては「就職への橋渡し役」として心強い存在になってくれますよ。
民間エージェントと並行して、ぜひ活用してみてください。
dodaチャレンジで断られたときの対処法について|よくある質問と回答
dodaチャレンジで「求人を紹介してもらえなかった」「面談後に断られてしまった」と感じると、不安や戸惑いを覚える方は多いです。でも実際には、その理由にはいくつかの傾向があり、決して自分だけが特別に断られたわけではありません。
大切なのは、断られた背景を理解し、それに合わせた対処法を考えることです。たとえば、スキル不足なら職業訓練や資格取得を、条件が厳しすぎるなら優先順位をつけて調整するなど、具体的にできることはたくさんあります。
この章では、そんな不安を和らげるために「よくある質問と回答」をまとめました。同じような経験をした人の声を参考にしながら、自分に合った次の一歩を見つけていきましょう。
dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
dodaチャレンジは、障がい者雇用に特化した就職支援サービスとして、多くの利用者から支持されています。
一方で、「求人の幅が少ない」「条件に合う求人が紹介されなかった」という声も一部に見られます。
特に、在宅勤務希望やスキルが未熟な場合などは、求人紹介が難しいケースもあるようです。
良い口コミとしては「キャリアアドバイザーの対応が親切だった」「自分に合った仕事を見つけられた」といった声も多く、総じてサポートの丁寧さが評価されています。
口コミはあくまで参考として、自分自身の状況に合ったサービスかどうかを見極めることが大切です。
関連ページ:dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
dodaチャレンジで断られてしまった場合でも、落ち込む必要はありません。
理由を明確にすることで、次のステップへとつなげることができます。
たとえば「スキル不足」が原因なら職業訓練や資格取得を、「条件が厳しすぎる」と言われた場合は希望条件の見直しを行うことが有効です。
また、dodaチャレンジ以外のエージェントやハローワークを併用することで、新たな選択肢が見えてくることもあります。
大切なのは、諦めずに「次の手」を打つこと。
行動することで、可能性は確実に広がっていきます。
関連ページ:dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
dodaチャレンジの面談後に連絡が来ない場合、いくつかの理由が考えられます。
たとえば「紹介できる求人がない」「条件に合う企業が見つからない」「確認や調整に時間がかかっている」などです。
ときには、連絡ミスやメールの不達といった単純な原因もあるので、自分から一度確認してみるのもひとつの手です。
待ってばかりでは不安が募ってしまいますよね。
気になるときは、遠慮せずに問い合わせてみましょう。
それも立派な自己管理の一歩です。
関連ページ:dodaチャレンジから連絡なしの理由と対処法/面談・内定・求人それぞれのケースと連絡なしの理由
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
dodaチャレンジの面談では、まずキャリアアドバイザーがあなたの希望条件や職務経験、障がいの内容、必要な配慮事項などをヒアリングしてくれます。
ここでは、無理に取り繕う必要はなく、正直に話すことが大切です。
面談の目的は「あなたに合った働き方を一緒に見つけること」なので、安心して臨んでくださいね。
聞かれる内容は、これまでの仕事経験、できる業務、働く上での希望条件、通勤状況などが中心です。
事前に話したいことをメモしておくと、スムーズに伝えられますよ。
関連ページ:dodaチャレンジの面談から内定までの流れは?面談までの準備や注意点・対策について
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がいのある方を対象にした就職・転職支援サービスです。
パーソルチャレンジ株式会社が運営しており、専門のキャリアアドバイザーが面談や求人紹介、面接対策などを行ってくれます。
一般的な求人サイトとは違い、ひとりひとりの障がいや希望に合わせたサポートが受けられるのが大きな特徴です。
職場での配慮事項や不安についても相談できるので、就職活動が初めてという方でも安心して利用できます。
障がい者雇用に特化した支援が受けられるのは心強いですよね。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
基本的に、dodaチャレンジでは「障がい者雇用枠」での求人紹介を行っているため、原則として障がい者手帳の所持が必要となります。
これは企業側が法定雇用率の達成を目的に採用を行っているためです。
ただし、障がい者手帳の申請中であったり、取得を予定している場合には、状況によって相談に乗ってもらえることもあります。
まずは現在の状況を正直に伝えて、登録可否を確認してみるのがよいでしょう。
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
dodaチャレンジでは、特定の障がいだからといって一律に「登録不可」とすることは基本的にはありません。
ただし、登録やサポートが難しいケースとしては「障がい者手帳を持っていない」「長期間のブランクがある」「就労が困難なほど体調が不安定」といった場合が挙げられます。
また、障がいの種類に関係なく、継続就労の見込みが立たないと判断された場合は、まずは「就労移行支援」の利用を勧められることもあります。
いずれにしても、まずは一度相談してみることをおすすめします。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
dodaチャレンジを退会したい場合は、電話または問い合わせフォームから手続きが可能です。
無理な引き止めなどはなく、スムーズに対応してもらえるので安心してください。
退会理由を聞かれることはありますが、それによって不都合が生じることはありません。
「就職が決まった」「他のサービスに切り替えることにした」など、状況に応じて丁寧に対応してもらえます。
個人情報の削除なども希望すれば対応してもらえるため、安心して申し出てくださいね。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングは、オンライン(Zoomなど)で行われるのが基本です。
自宅から参加できるので、身体的な負担が少なく、安心して相談できるのがうれしいポイントです。
もちろん、スマホやパソコンがあれば簡単に参加できます。
対面でのカウンセリングを希望する場合は、地域や状況によって応じてもらえることもありますが、まずはオンラインが基本と考えておくと良いでしょう。
準備や使い方が不安な場合は、事前に案内してもらえます。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
dodaチャレンジのサービスに年齢制限は設けられていません。
若年層から中高年の方まで、幅広い世代が利用することが可能です。
ただし、実際に紹介される求人の傾向としては「20代〜50代前半」が中心になっているため、年齢が高くなるほど求人が限られる傾向はあります。
だからといって登録ができないわけではないので、まずは相談してみることが大切です。
自分に合った働き方や条件を一緒に見つけてくれるパートナーとして活用しましょう。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
はい、離職中の方でもdodaチャレンジのサービスを利用することができます。
実際、転職活動中やブランクがある方の相談も多く、再就職に向けたサポートがしっかり受けられるようになっています。
キャリアアドバイザーがこれまでの職歴やスキルを整理してくれるほか、「今の自分に何ができるか」を一緒に考えてくれるので、不安が大きい方にもおすすめです。
離職期間がある場合も、正直に伝えれば大丈夫ですので、安心して登録してみてくださいね。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
dodaチャレンジは基本的には「卒業後の就職・転職」を対象としたサービスであるため、在学中の学生さんの求人紹介は行っていないことが多いです。
ただし、卒業間近で就職先を探している場合や、障がい者手帳を取得予定で進路相談をしたいときは、相談だけでも可能な場合があります。
もし学生さんで将来の就職に不安がある場合は、大学の障がい学生支援窓口や就職課と連携しながら、dodaチャレンジにも相談してみると安心です。
参照:よくある質問(dodaチャレンジ)
dodaチャレンジは断られない?その他の障がい者就職サービスとの比較一覧
「dodaチャレンジに登録したら断られてしまった…」という声を聞くと、不安になってしまいますよね。
でも実際には、どの障がい者就職サービスでも「すべての人に求人を紹介できる」というわけではありません。
サービスごとに得意分野や対象となる条件が違うからです。
たとえば、dodaチャレンジは事務系や大手企業の求人に強みがある一方で、atGPは在宅ワークに対応していたり、サーナは合同面接会の開催に力を入れていたりと、それぞれ特色があります。
もし一つのサービスでうまくいかなくても、他を併用することで新しい可能性が広がるんです。
「断られた=就職できない」ではなく、「ここ以外に合う場所があるかもしれない」と前向きに考えることが大切ですよ。
| 就職サービス名 | 求人数 | 対応地域 | 対応障害 |
| dodaチャレンジ | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| アットジーピー(atGP) | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| マイナビパートナーズ紹介 | 350 | 全国 | 全ての障害 |
| LITALICOワークス | 4,400 | 全国 | 全ての障害 |
| 就労移行支援・ミラトレ | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| ランスタッドチャレンジ | 260 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪 | 全ての障害 |
| Neuro Dive | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| Cocorport | 非公開 | 首都圏、関西、東海、福岡 | 全ての障害 |
dodaチャレンジで断られた!?断られた理由や対処法|難しいと感じた詳しい体験談まとめ
dodaチャレンジで「断られた」と感じるのは、決して自分だけではありません。
希望条件が合わなかったり、スキルや経験が不足していたり、体調や生活の安定が求められたりと、その理由はさまざまです。
でも、断られることは「終わり」ではなく、「次に向けての課題が見えた」という大切なサインでもあります。
スキルを磨く、条件を見直す、他のサービスを併用するなど、できることはたくさんあるんです。
実際に体験談を振り返ると、どの方も最初は壁にぶつかりながら、少しずつ次の道を見つけています。
就職活動は一度で成功するものではありません。
大切なのは「諦めないこと」と「柔軟に工夫すること」。
あなたにもきっと、自分に合う働き方や職場が見つかるはずです。
焦らず、自分のペースで進んでいきましょうね。