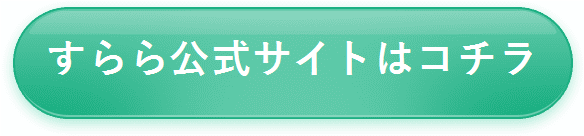すららは不登校でも出席扱いになる?なぜ?出席扱いになる理由について
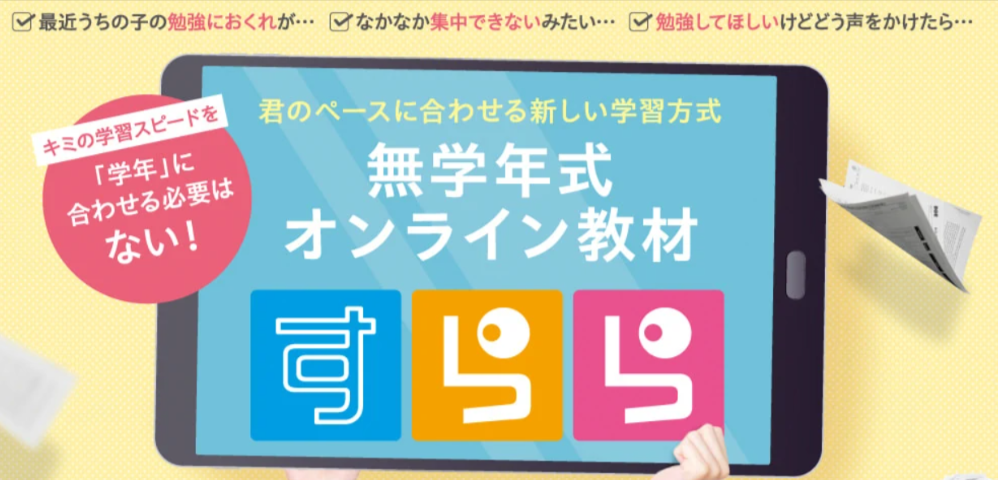
不登校の子どもが自宅で学ぶ場合、「学校の出席としてカウントされるのかどうか」は、保護者にとって非常に重要なポイントです。
すららは、文部科学省が提示している出席扱いのガイドラインに対応しており、学習記録の管理・提出、継続的な学習支援、学校との連携などが評価され、実際に多くの子が出席扱いを認定されています。
本記事では、すららがなぜ出席扱いになりやすいのか、その根拠となる理由を5つの視点でわかりやすく解説していきます。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららは学習の「質」と「記録性」において、学校側からも高く評価されやすい教材です。
学習の履歴が自動的に保存され、日々どの教科をどれだけ勉強したか、どのくらい理解しているかなどの情報が一目でわかる「学習記録レポート」を出力できます。
これは、学校に提出できる形式として整えられており、保護者の手間なく、客観的な証明資料として活用できます。
このような可視化された学習の証拠があることで、学校側も安心して出席扱いに認定しやすくなっています。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
学習記録レポートは、単元別の進捗や正答率、取り組んだ時間までしっかりと記録されており、担任や学校側へ提出することで、教育活動の一環としての証明になります。
これにより、子どもが「家でしっかり学んでいる」ということが数値化され、評価対象になりやすくなります。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
忙しい保護者が毎日の記録を手作業で残す必要がないのも、すららの大きな魅力。
子どもがタブレットで学習するだけで、すべての履歴が蓄積されていき、レポート形式で簡単に出力できます。
先生側もこれを見るだけで、十分な学習の証拠と判断してくれるケースが多いです。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
不登校の子どもにとって、「学習を続けられるか」は非常に大きな課題です。
すららは、専任のコーチが子どもの状態に合わせた学習計画を作成してくれるため、ムリなく・ムダなく学習を継続しやすいのが特長です。
子どもの理解度や生活リズムに応じて、柔軟に調整できるので、精神的な負担が軽く、継続性にもつながります。
このように、計画性と継続性がセットであることが、「出席扱いの条件」にしっかり対応できる理由の一つです。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
「ただ教材を渡して自習させる」ではなく、すららコーチが個々の状況を確認しながら伴走してくれるため、学習内容に説得力が生まれます。
学校側に対しても「継続的な学び」が行われていることを明確に示すことができます。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
すららのコーチは、保護者と相談しながら現実的な学習スケジュールを提案してくれます。
「やらせっぱなし」にならず、日々の小さな達成を積み重ねる形で学びの軌道に乗せてくれるのがポイントです。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
学年に縛られず、得意な教科は先取り、苦手な教科は戻って復習できる“無学年式”のすららは、つまずきを感じやすい不登校の子にもピッタリ。
これが出席扱いの認定において「合理的な個別対応」として評価されるケースもあります。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
出席扱いを認定してもらうには、家庭だけではなく学校側との連携も必要不可欠です。
すららは、学習レポートの作成支援や提出方法の案内、学校との連絡に関するアドバイスなども丁寧にフォローしてくれます。
担任や校長とのやりとりに不安がある保護者にとって、すららの存在は大きな心の支えになるはずです。
「親・学校・教材提供側」が同じ方向を向いて子どもの学びを支えてくれる環境があるからこそ、出席扱いとしての認定がスムーズに進みやすいのです。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
すららでは、学習記録を提出するための書類やレポートの書き方、どのタイミングで誰に渡すべきかなど、細かい部分までガイドが用意されています。
学校への説明が必要な場面でも困りません。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
すららでは、出席扱いの申請に必要な「学習記録の提出書類」について、専用のレポートフォーマットを用意してくれます。
そして、その記入方法や提出タイミングまで、専任のすららコーチが丁寧にフォローしてくれるのも大きな特徴です。
保護者の方は、「何を書けばいいの?」「どれを出せばいいの?」と悩みがちですが、コーチからのサポートがあることで安心して対応できます。
提出すべき学習成果を分かりやすく整理してくれるため、学校側にも伝わりやすく、結果として出席扱いとして認められやすくなるのです。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
不登校の子どもを支えるには、保護者が学校側としっかり連携を取る必要があります。
しかし、「どう話を切り出せばいいか分からない」「担任や校長先生に何を説明すればいいのか…」という不安を抱える親御さんも多いもの。
すららでは、学校との連携をスムーズに行うための「サポート情報」や「書面の見本」、場合によっては学校向けの説明資料も提供してくれます。
こうした“後押し”があるからこそ、先生とのコミュニケーションも前向きに進めやすくなり、出席扱いの理解も得やすくなるのです。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、「不登校児童生徒への学習支援に対応した教材」として、文部科学省のガイドラインに準拠しています。
つまり、“ただのタブレット学習”ではなく、「家庭で学んだ学習成果を出席扱いとみなすために必要な条件」をクリアしている教材ということ。
実際、すららは全国の自治体や学校と連携しており、すでに多くの不登校の子どもたちが「出席扱い」の認定を受けています。
教材の信頼性はもちろん、公式に認められた実績があるからこそ、保護者も学校側も安心して利用できるのです。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは、これまでに数多くの学校・教育委員会と連携し、不登校支援に取り組んできた実績があります。
出席扱いの申請において、「すららを使っていたら話が早かった」「学校側が教材名だけで理解してくれた」といった声も実際に多く聞かれます。
この“安心の前例”があるからこそ、初めて出席扱いに取り組む家庭でも、すららを選ぶ価値があると言えるのです。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
文部科学省が出しているガイドラインでも紹介されるほど、すららは「不登校対応教材」としての信頼を得ています。
教材内の仕組みやレポート機能など、すべてが“学校側に説明しやすい構成”でつくられているため、公式に不登校支援として利用されている実績があるのも納得です。
出席扱いだけでなく、子ども自身の学習自信や自己肯定感を育てる点でも、すららは頼りになる存在です。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
出席扱いの条件の一つに、「学習環境が学校に準じていること」が挙げられます。
つまり、ただ家で勉強しているだけでは難しく、「教育課程に沿った内容で学び、評価もできる仕組みがあるか」が重視されます。
すららでは、小中高すべての教科で文部科学省の学習指導要領に準拠した内容が提供されており、しかもAIが理解度を判断しながら進行。
学習結果はグラフや数値で可視化され、先生側にも「ちゃんと勉強している」と伝わる構成です。
こうした“システム的な学習管理”ができるからこそ、「学校に準じた環境」として認定されやすいのです。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららの教材は、文部科学省が定める学習指導要領にしっかり準拠しています。
つまり、家庭での学習であっても、「学校で学ぶ内容と同じ質・範囲の勉強ができる」ということ。
この点が出席扱いを認めてもらう際には非常に大切で、学校の先生に説明するうえでも「同等の教育を受けている」と伝えやすくなります。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
すららでは、学習の進捗や理解度がグラフや数値で視覚化され、学習後にはフィードバックも自動的に行われる仕組みがあります。
この「学んだ→結果が見える→次に活かす」というサイクルがしっかり機能していることで、学校側にも「評価可能な学習システム」として受け入れられやすくなります。
これは、“ただの教材”ではなく、“教育環境の代替”として認められるための大きなポイントです。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法の流れ紹介
不登校の子どもが家庭学習をしている場合、その学習が「出席扱い」になる制度があるのをご存じでしょうか?文部科学省の通知により、一定の条件を満たせば自宅での学習も学校の出席とみなすことができるようになっています。
すららはこの制度に対応した教材の一つであり、実際に多くのご家庭がこの仕組みを活用して、子どもの学びを支えています。
ここでは、すららを利用して出席扱いを申請する方法を4つのステップに分けて解説します。
初めての方でもわかりやすいように、必要書類や注意点も併せて紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
申請方法1・担任・学校に相談する
まず最初に行うべきは、担任や学校との相談です。
どれだけ家庭で学習を頑張っていても、学校側が出席扱いを認めなければ制度は適用されません。
出席扱いは校長の判断で決まるため、早めに学校側と話し合い、制度の利用意思を伝えることが大切です。
その際には、「すららを使って学習している」「定期的に進捗を確認している」といったことを丁寧に説明するようにしましょう。
学校によって手続きの流れが異なる場合もあるため、必要書類や申請タイミングについてもここで確認しておくのがスムーズです。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
学校に相談すると、「この書類を揃えてください」とリストを渡されることがあります。
主に求められるのは学習記録、学習内容の概要、場合によっては医師の意見書などです。
また、「週に何日以上学習しているか」「どの教科をどのくらい取り組んでいるか」など、出席扱いの条件を明確に聞いておきましょう。
すららの学習レポートは、これらの証明に役立つ重要な資料になります。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
不登校の理由が心身の健康状態による場合、医師の診断書が必要になるケースがあります。
特に「心理的理由」「適応障害」「発達障害」などが原因で学校に通えない場合は、医師の意見が出席扱いの判断材料になります。
すべての家庭に必要なわけではありませんが、学校側から提出を求められた場合には準備が必要です。
早めに受診し、学習継続の意義を明確に書いてもらうことが大切です。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
診断書の提出は、特に「医療的ケア」「心理的サポート」が求められる不登校ケースで多く見られます。
これは学校が「医学的な正当性があるかどうか」を確認したい意図があるからです。
診断書には、通学困難の理由だけでなく、「家庭学習を推奨する」といったコメントがあると出席扱いがスムーズになる場合があります。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書は、子どもの状態を正確に伝えるものであると同時に、学習継続の必要性を学校に伝えるツールでもあります。
医師には、すららなどの教材で家庭学習をしている旨を説明し、「学びを止めない選択肢として適している」ことも伝えてもらうと、学校側も前向きに受け止めてくれることが多いです。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
出席扱いの申請においてもっとも重要なのが「学習の実績を証明する資料」です。
すららには、子どもがどの単元をどのくらいの時間学習し、どんな成績だったかがわかる「学習進捗レポート」があります。
これをPDFなどで出力し、担任や校長先生に提出します。
また、出席扱い申請書自体は学校側が作成しますが、保護者が記入すべき項目もあるため、連携しながら書類を完成させていきましょう。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららのマイページから、子どもが学習した履歴をレポート形式で出力できます。
日時や内容、正解率などが記録されているため、学習の“証拠”として非常に信頼性が高く、学校側にとっても確認しやすいのが特徴です。
これを月単位などで提出することで、定期的な確認・承認を得やすくなります。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
出席扱い申請書は基本的に学校が用意してくれますが、家庭学習の状況や教材内容について保護者が記入する欄が設けられていることが多いです。
すららの特徴やコーチのサポート内容、教材の構成などを具体的に書くと、校長先生の判断がしやすくなります。
わからない場合は、すららコーチに相談するとスムーズです。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
必要書類をすべて整え、担任との相談も済んだら、最後に学校長(校長先生)の承認が得られるかどうかがポイントです。
出席扱いは学校長の裁量で判断されるため、事前の信頼関係がとても重要です。
学校によっては、さらに教育委員会への報告や承認が必要になる場合もあります。
すららのような実績のある教材を使用していると、話がスムーズに通りやすくなる傾向があります。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
校長先生が、提出された学習記録や家庭の状況を見て「学校に準ずる学習が行われている」と判断すれば、出席扱いが認められます。
この際、学習の継続性や教材の信頼性が大きな判断材料になりますので、すららのようなサポート体制が整っている教材は非常に有利です。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
一部の自治体では、出席扱いを教育委員会に申請する必要がある場合もあります。
その場合、保護者が直接やり取りをすることはほとんどなく、学校側が中心となって進めてくれます。
すららのサポートチームも、こうした自治体ごとの対応に慣れているので、困ったときは遠慮せず相談しましょう。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて解説
不登校の子どもが「出席扱い」を受けられるというのは、単に記録上の話にとどまらず、進路や心の健康にも大きな影響があります。
すららは、不登校でも家庭での学習をしっかりサポートし、その努力を「出席」として認めてもらえる環境を整えてくれます。
この制度を活用することで、内申点を守ったり、進学に必要な条件を満たしたりと、子どもと保護者にとって実はとても重要な意味を持ちます。
ここでは、すららを通じて出席扱いを受けることで得られる3つの大きなメリットを紹介します。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
出席日数は、内申点の評価に大きく影響します。
不登校が続いて欠席扱いが増えてしまうと、たとえテストの点数が良くても内申が下がってしまう可能性があるのです。
しかし、すららでの学習が出席扱いとして認められれば、出席日数をカウントしてもらえるため、成績評価でマイナスになりにくくなります。
これは中学校や高校に進学する際の内申書において、非常に大きな意味を持ちます。
「不登校=進路が狭まる」という不安が、ぐっと軽減されるでしょう。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
テストの成績だけでなく、出席状況も内申点の重要な評価基準の一つです。
すららで出席扱いを受けることで、「無断欠席が多い」と見なされることを防ぎ、内申点が安定しやすくなります。
これはとくに公立高校の選抜において大きな意味を持ちます。
中学・高校進学の選択肢が広がる
出席扱いによって出席率が一定以上保たれると、選べる学校の幅が広がります。
「欠席が多いと志望校が限られるのでは」と心配している保護者にとって、すららを活用して出席日数を確保できることは、進学面での安心材料になります。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校になると、教室での授業に遅れてしまうことへの不安がつきまといます。
「みんなは先に進んでいるのに、自分は分からないまま…」という感覚は、子どもの自信を大きく削ってしまいます。
すららは無学年式なので、子どもが今どこでつまずいているかを分析し、その部分からやり直すことができます。
理解が深まったあとに次のステップへ進めるため、「取り残されている」感覚を抱かずに学習を続けられます。
これが、学びに対する前向きな気持ちを取り戻す大きなきっかけになるのです。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
毎日少しずつでも学び続けていれば、「みんなと違う」という焦りを感じにくくなります。
無理のないペースで基礎から復習できるすららのスタイルは、授業の進み具合に左右されず、自分のペースで着実に進める安心感があります。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
「学校に行けていない自分はダメなんじゃないか…」そんなふうに思ってしまう子どもは少なくありません。
でも、すららを通じて「今日はここまで頑張れた」と実感できることで、少しずつ自信を取り戻していくことができます。
これが長期的には「学校に戻りたい」という気持ちにつながることもあります。
メリット3・親の心の負担が減る
子どもが不登校になると、「どうサポートすればいいの?」「進学はどうなるの?」と保護者もたくさんの不安を抱えることになります。
とくに学習の遅れや、出席日数の不足が進路にどう響くのかを心配して、夜も眠れないという声も少なくありません。
すららは、学習面だけでなく「すららコーチ」がついて親子をサポートしてくれるため、相談できる相手がいるというだけでも気持ちが軽くなります。
学校とのやりとりやレポート作成の手助けもあるので、保護者がひとりで背負い込まなくて済むのが大きなメリットです。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
「わが家だけでなんとかしなきゃ」と思わなくて大丈夫です。
すららには、家庭と学校の間に立ってくれる専任コーチがいます。
必要書類の準備や提出のフォローもしてくれるので、出席扱いの手続きに関しても心強い味方となってくれます。
孤独に戦わなくていいのは、本当にありがたいですね。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための重要な注意点について解説
すららを使って家庭学習を続けている場合、「出席扱いにしてもらえるかどうか」が大きな関心ポイントになりますよね。
すららは文部科学省のガイドラインに沿った教材なので、条件を満たせば正式に「出席扱い」として認定される可能性があります。
ただし、スムーズに認められるためには、いくつかの注意点をしっかり押さえておく必要があります。
ここでは、出席扱い申請でつまずかないために、事前に確認しておきたい3つの注意点を紹介します。
学校や医師との連携、学習内容の質など、見落としがちな部分にもしっかり触れています。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
出席扱いが認められるかどうかは、最終的に「校長先生の判断」によるため、学校との信頼関係と情報共有が非常に重要です。
担任の先生にだけ話していても、学校全体として理解が得られなければ申請はスムーズに進みません。
そのため、出席扱いの制度やすららの特長について、丁寧に学校側に伝えることが大切です。
とくに「すらら=文科省ガイドラインに準拠した教材である」という点は、学校関係者が安心して判断するための重要な材料になります。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
「家庭学習をしています」と言うだけでは、学校側は「どんな教材を使って?どうやって?」と疑問を抱きます。
そこで「すららは文部科学省が出席扱い制度において示す条件を満たした教材である」ことを伝えることで、信頼性が高まり、学校側も前向きに受け入れやすくなります。
資料を用いて具体的に説明するとより効果的です。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
担任の先生だけに説明していても、実際に判断するのは教頭や校長です。
できれば初期段階で校長先生にも直接相談の機会を設け、家庭の状況や子どもの学習実績を共有しておくことが望ましいです。
すららのパンフレットやレポート出力例など、客観的に説明できる資料を一緒に持っていくことで、理解が得られやすくなります。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
不登校の原因によっては、家庭での学習が続いていても出席扱いにはならないケースもあります。
とくに精神的な不安や適応障害などが背景にある場合、医師の診断書が求められることが多いです。
これは、「なぜ学校に通えていないのか」「家庭学習が適切な選択であるのか」を第三者の専門家が証明するためのものです。
事前に通院している病院に相談し、出席扱い申請用に記載してもらえるようお願いしておくとスムーズです。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
特に長期間にわたる不登校の場合は、家庭だけで対応していると「保護者の判断で登校させていない」と誤解されることもあります。
医師の診断書があれば、「学校に通えない正当な理由がある」ことを裏付けられるため、学校側も安心して判断しやすくなります。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
医師に診断書をお願いする際は、「文科省の制度で出席扱いにしたいので、診断書をお願いします」と具体的に伝えましょう。
病院によっては、出席扱いの制度を知らないこともあるため、制度の概要を簡単に説明できるようにしておくとベストです。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
医師が診断書を書くにあたって、家庭での学習状況や子どものやる気を知っておく必要があります。
「毎日○分すららに取り組んでいる」「学習意欲は高い」といった情報を共有することで、診断書に前向きな内容が記載され、学校側の承認も得やすくなります。
注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
すららを利用していても、「自由に好きなことをしているだけ」では出席扱いにはなりません。
文科省のガイドラインでは「学校の授業と同程度の学習内容」「指導要領に基づく教材」が求められています。
すららは国語・数学・理科・社会・英語の5教科をカバーし、教科書レベルのカリキュラムで構成されているため、十分にこの条件を満たしていますが、それを“見える化”して学校に伝えることが必要です。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
家庭で学習していると言っても、内容がゲーム感覚の教材だったり、ただの読書であったりすれば、学校側としては評価が難しくなります。
すららのように教科ごとにカリキュラムが整っており、単元ごとの理解度が記録されるシステムであれば、学校も「学校教育に準じた学び」として判断しやすくなります。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
出席扱いとして認められるためには、家庭での学習時間が「学校に準じている」と判断される必要があります。
小中学生であれば、1日に2〜3時間程度の学習を継続することがひとつの目安です。
ただし、学年や本人の体調・状態に応じて柔軟に調整して構いません。
大切なのは「その子なりの習慣と継続性」があること。
すららは1単元が10~15分で区切られているので、1日に複数ユニットを計画的にこなすことで、学校に近い学習ボリュームを確保できます。
日々の学習状況を記録しながら、無理のない範囲でペースを作っていきましょう。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
出席扱いの条件には「教育課程に準じた学習内容」が含まれており、主要3教科(国・数・英)だけでは不十分と判断されることもあります。
学校の学習指導要領に従い、理科・社会も含めた5教科をバランスよく学ぶことが望ましいとされています。
すららなら、無学年式で全教科をカバーできるため、この条件もクリアしやすいです。
苦手な教科を後回しにせず、週ごと・月ごとに計画を立てて進めていくことで、出席扱いの継続にもつながります。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
すららを使って出席扱いを受ける場合、学校との“定期的なやり取り”が不可欠です。
単に学習しているだけではなく、「その内容と状況を学校と共有している」ことが大前提となります。
特に、学習成果の報告や進捗確認があるかどうかは、学校長が出席扱いを判断するうえで非常に重視されるポイントです。
すららでは、学習レポートを簡単に出力できる機能があるため、これを毎月提出するなど、学校との信頼関係を築いていくことが大切です。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
文部科学省のガイドラインでは、家庭と学校との間で「学習状況の共有があるかどうか」も出席扱いの判断基準とされています。
学習レポートを提出したり、面談で説明したりと、学校に情報をきちんと伝えていくことで、理解と信頼を得られやすくなります。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららには、保護者用ページからダウンロードできる「学習進捗レポート」があり、これを月に1回程度提出するのが理想です。
提出することで、継続的に学んでいることを証明でき、出席扱いの継続判断にも良い影響を与えます。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
学習状況やお子さんの様子をより具体的に把握したいという学校側の意向に応じて、家庭訪問や面談の機会が設けられることもあります。
こうした依頼には柔軟に応じることで、信頼関係の構築にもつながり、申請がスムーズに進むことが多いです。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
学習記録だけでなく、「今日は調子が良かった」「この教科が苦手そう」など、日々の小さな変化も共有しておくと、先生の理解が深まります。
月1回の提出とは別に、メールや電話でこまめに報告しておくことで、先生との信頼関係が深まり、出席扱いもスムーズに認められやすくなります。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
出席扱いの申請は、原則として校長の判断によって決まりますが、一部の自治体では教育委員会の承認が必要なケースもあります。
その場合、学校を通じて正式な書類を提出したり、教育委員会側の指示に従って追加書類を用意する必要があります。
どのような資料が求められるかは地域によって異なるため、まずは学校に確認し、すららの学習記録や診断書をもとに準備を進めましょう。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会への申請が必要な場合、学校側と連携しながら慎重に準備を進めていくことが大切です。
すららの学習記録、医師の診断書、本人の学習意欲を伝える文書など、どの資料が必要かを学校に相談しながら整えていくことで、教育委員会とのやり取りもスムーズになります。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを解説
すららを利用して出席扱いを申請し、無事に承認されるまでには、いくつかの“成功のコツ”があります。
ただ教材を使って学習しているだけではなく、「どのように学校に伝えるか」「どんなサポートを活用するか」「本人の意欲をどう見せるか」など、工夫次第で結果が変わってくるのが出席扱い制度の難しさでもあり、面白さでもあります。
ここでは、すらら利用者の中でも成功事例が多かった「具体的な成功ポイント」を4つにまとめてご紹介します。
これから申請を考えている方、学校とのやりとりに不安を感じている方にとって、きっとヒントになるはずです。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
学校の先生方は、「自分たちが前例のないことを承認する」ことに慎重になりがちです。
だからこそ、すでに他校での出席扱い事例を紹介して、「すららは実績のある教材なんだ」と認識してもらうことがとても効果的です。
すらら公式サイトでは、不登校対応の実績や、出席扱いとして認められた具体的な学校名・地域なども紹介されており、それを印刷して学校に持参することで、先生の安心感を高めることができます。
説得ではなく“納得”してもらうために、信頼性の高い情報を活用しましょう。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
「他の学校で通ったなら、うちでも可能性があるかもしれない」と思ってもらうことは大切なステップです。
公式な事例紹介は、教員にとっても説得力のある情報源となります。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
インターネット上で見せるだけでなく、紙で渡せる資料として持って行くと、校内での共有もしやすくなります。
「ここに書いてあります」と手渡せば、その場で読んでもらいやすいです。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
出席扱いの申請で重要視されるのは、保護者の希望だけでなく「本人が学習意欲を持って取り組んでいるか」です。
それを伝えるために、本人が書いた感想や学習目標、日々の気づきなどを提出資料として添えるのが効果的です。
また、面談が設定された場合には、本人も一緒に出席し、自分の言葉で「頑張っていること」「これからも続けたい気持ち」を話すことができれば、先生方の心にも響きやすくなります。
無理に完璧を求める必要はありません。
小さな言葉でも、「本人のやる気」が伝われば、結果は大きく変わります。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
ノートに手書きで書いた学習日記や、Wordで作った短いコメントでも構いません。
「今週は英語が楽しかった」「漢字がちょっと苦手だったけど頑張った」など、正直な気持ちでOKです。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
本人が直接話すことで、先生方も「この子は本当に取り組んでいるんだ」と実感できます。
うまく話せなくても問題ありません。
表情や態度だけでも、十分に気持ちは伝わります。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
出席扱いの申請が通った後も、「継続して学び続けること」が大きな条件になります。
無理なスケジュールで始めても、途中で挫折してしまえば、学校側も「やっぱり継続できなかった」と再評価してしまうリスクがあります。
だからこそ、最初から“本人にとって無理のないペース”で学習計画を立てておくことが大切です。
すららのコーチに相談すれば、お子さんの状態や得意不得意に合わせた現実的なプランを提案してもらえます。
継続こそ最大の信頼材料。
自信をもって取り組める設計を最初に整えておきましょう。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
毎日3時間の学習が理想だとしても、現実には30分しか集中できないこともあります。
それでも大丈夫。
「毎日30分×1ヶ月続ける」方が、実績としても評価されやすいです。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
無理のない計画を立てるには、すららコーチの存在が非常に心強いです。
AI診断結果も活用しながら、本人のペースと課題に合わせた学習スケジュールを一緒に作成してくれます。
ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する
すららには、単なる自動学習システムではなく、専門の「すららコーチ」が個別にサポートをしてくれる体制があります。
出席扱いを目指す場合、学習の継続だけでなく、レポート提出や学校対応など、細かい点での支援が必要になります。
すららコーチは、出席扱い制度にも精通しているため、「どの情報をどのように学校に出せばよいか」「学習記録をどう活用するか」など、実務的な相談にものってくれます。
迷ったときには一人で悩まず、コーチに頼ることが、安心して進めるための近道です。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
すららの管理画面から出せるレポートはとてもわかりやすく、学校への提出にも適していますが、「この期間のデータで大丈夫かな?」「どの項目を強調すべき?」と不安になったときは、すららコーチが親身になってアドバイスしてくれます。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミ・評判を紹介します
不登校のお子さんを持つご家庭にとって「すららを使えば出席扱いになるの?」という疑問はとても気になるポイントです。
文部科学省の方針では、ICT教材を活用した学習が一定の条件を満たせば「出席扱い」と認められる場合があります。
すららはその対象教材のひとつとして学校で導入されているケースがあり、学校や教育委員会との連携によって自宅学習が出席にカウントされることもあります。
実際の口コミでは「すららを利用して学校と相談した結果、出席扱いになった」「安心して学習を続けられた」という前向きな声が多い一方で、「学校によって対応が異なり、必ずしも出席扱いになるわけではなかった」という意見もあります。
つまり、すらら自体が出席扱いを保証するわけではなく、あくまで学校側との調整次第という点に注意が必要です。それでも「学習を止めずに続けられる安心感」が大きなメリットとして評価されています。
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問と回答
「すららを使えば不登校でも出席扱いになるの?」という質問はとても多く寄せられます。結論から言うと、すららは文部科学省が出席扱いの対象として認めているICT教材の一つですが、必ず出席扱いになるとは限りません。
実際には、学校や教育委員会の判断によって取り扱いが異なるのが現状です。
そのため、利用を検討している場合は、まず担任の先生や学校側に相談し「家庭学習を出席扱いにできるかどうか」を確認することが大切です。
口コミの中には「学校と連携して出席扱いになった」「学習状況を報告して認めてもらえた」という前向きな声もあれば、「学校の方針で出席扱いにならなかった」というケースもあります。いずれにしても、すららを利用して家庭で学習を続けることは、子どもにとって学力の維持や自信の回復につながる大きな支えとなります。
出席扱いの可否だけにとらわれず、安心して学習を継続できる環境づくりに役立てるのがおすすめです。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
すららに「うざい」といった口コミが寄せられる理由には、学習の継続に難しさを感じたり、AIキャラの口調に違和感を覚えたりするなど、個人差のある体験が影響しています。
ただし、これは決して教材の質が低いという意味ではありません。
自分のペースで進められる反面、自主性が求められるため、サポートなしでは合わない子もいるのです。
逆に「自分で考えて進める力がついた」「不登校の子にもやさしい設計」と高評価する声も多く、好みや状況によって評価が分かれる教材といえます。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには「発達障害専用コース」というものはありませんが、発達障害のある子どもに特化した学習設計が取り入れられています。
ユニバーサルデザインに基づいた画面構成、音声ナビゲーション、アニメによる解説など、視覚・聴覚にやさしい工夫が満載です。
ADHDやASD、LDなどの子でも安心して使えるように、すららコーチが学習計画を柔軟に調整してくれる点も好評です。
料金は一般向けと同一で、障害の有無で差別的な価格設定はされておらず、公平に学べる体制が整っています。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
はい、すららは文部科学省のガイドラインに対応した教材として、多くの学校で「出席扱い」の対象として認められています。
不登校の状態にあっても、学習内容・記録・サポート体制が整っているため、学校に「すららを通じて学習を継続している」と報告すれば、出席日数としてカウントされることがあります。
必要書類の整え方や申請の流れも、すらら公式やすららコーチが案内してくれるため、保護者も安心して取り組むことができます。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららでは、時期に応じて「入会金無料」や「教材費割引」などのキャンペーンコードが配布されることがあります。
入会手続き時に専用フォームへコードを入力するだけで簡単に適用でき、初期費用を抑えたいご家庭にとっては非常に助かる仕組みです。
キャンペーンコードは公式サイトやメールマガジン、提携サイトで配布されていることが多いので、申し込み前には必ずチェックしましょう。
有効期限があるため、古いコードを使わないように注意が必要です。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららを退会する際は、「解約」と「退会」の違いに注意が必要です。
解約は毎月の支払いを停止し、学習を終了する手続きで、電話による受付のみとなっています。
登録者の名前やID、連絡先などを伝えて本人確認を行い、希望する月の解約日を指定する形になります。
退会は、解約後に会員情報を完全に削除するステップで、こちらも電話で依頼できます。
学習履歴を残しておきたい場合は解約のみで留めておく家庭も多いです。
関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららの料金体系はとてもわかりやすく、「入会金+月額料金」のみです。
テキスト代や教材費、サポート費といった追加費用は一切かかりません。
すららのすべての教材はオンライン上で提供されるため、紙の教材を買い足す必要もなく、タブレットかパソコンがあればすぐに始められるのが大きな特長です。
通信環境だけは各家庭で用意する必要がありますが、それ以外は料金体系が明確で、月々の負担も予測しやすい安心設計です。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららでは、1人の契約につき1人専用のアカウントが発行されます。
そのため、兄弟や姉妹とアカウントを共有して利用することはできません。
すららの学習は個別最適化されており、AIによる弱点分析やコーチによる学習計画は、本人の進捗状況に基づいて作成されるからです。
ただし、兄弟で同時入会した場合、入会金の割引などのキャンペーンが適用されることもあるため、事前に公式サイトで最新情報を確認しておくとよいでしょう。
すららの小学生コースには英語はありますか?
はい、すららの小学生コースには英語も含まれています。
英語の基本となるあいさつや単語、フォニックスをはじめとした音の仕組みなどを、アニメーションと音声ナビで楽しく学べる構成になっています。
英語を初めて学ぶ子でも「わかる」「できる」を実感しやすく、英語嫌いにならずに進められると好評です。
読み・書き・聞く・話すをバランスよく身につけられるように設計されており、将来の中学英語への準備としても非常に役立つ内容です。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららでは、学習の進捗やつまずきに応じて「すららコーチ」が個別にサポートしてくれます。
すららコーチは、子どもの特性や学習スタイルに合わせて、無理のないスケジュールを提案したり、学習のモチベーションを維持する工夫を教えてくれたりと、保護者の不安にも寄り添ってくれる存在です。
発達特性があるお子さんにも理解があり、親子で一緒に学習を支える体制が整っているのが、すららの大きな魅力です。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材との違いを比較しました
不登校になったとはいえ、「学校とのつながりを保ちたい」「出席扱いにして進学に影響を出したくない」というご家庭にとって、どのタブレット教材を選ぶかはとても重要です。
中でもすららは、学校へのレポート提出や教育委員会への対応のしやすさで高評価を受けており、多くの出席扱い事例があります。
この記事では、すららと他の家庭用教材との違いを、制度対応力・学習管理機能・学校との連携のしやすさという視点で詳しく比較しています。
制度を活用して、少しでも子どもの未来を広げたい方に参考になる内容です。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。
|
16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・注意点・申請手順まとめ
お子さんが不登校になったばかりのご家庭にとって、まず気になるのが「このまま学校に通えなくても大丈夫なのか」という不安ではないでしょうか。
実は、自宅での学習でも「出席扱い」にできる制度があり、すららはその条件をクリアしている教材のひとつです。
この記事では、出席扱い制度の仕組みから、申請時に必要な書類、注意すべき点までわかりやすくまとめました。
今はまだ混乱しているかもしれませんが、少しずつ情報を整理しながら、お子さんの未来に向けて前向きに動き出しましょう。